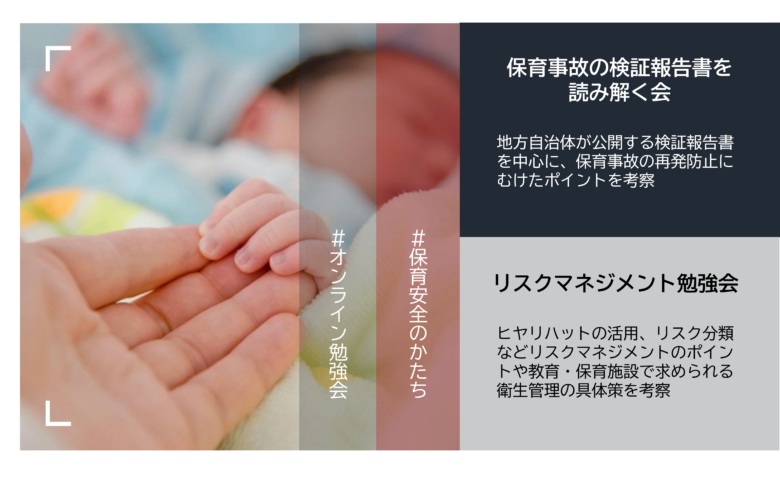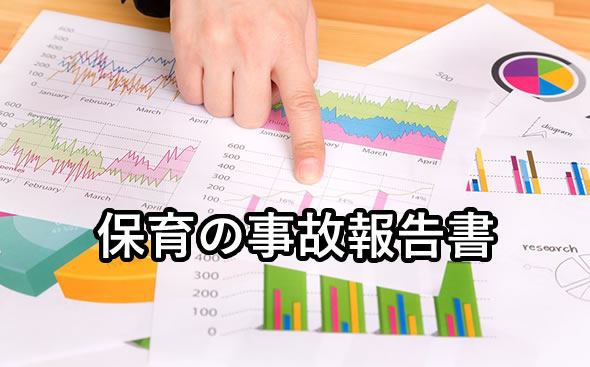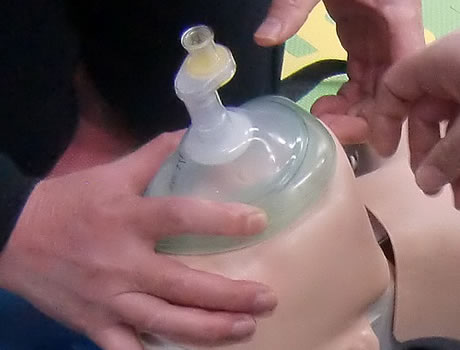保育安全のかたちは
保育の安全管理(リスクマネジメント)を通じて
子どもが心身ともに健やかに育つ権利を守ります
パンデミック(感染爆発)で
園児の命が脅かされる 保育環境の危機が訪れました
こうした今こそ安全管理を見なおしましょう
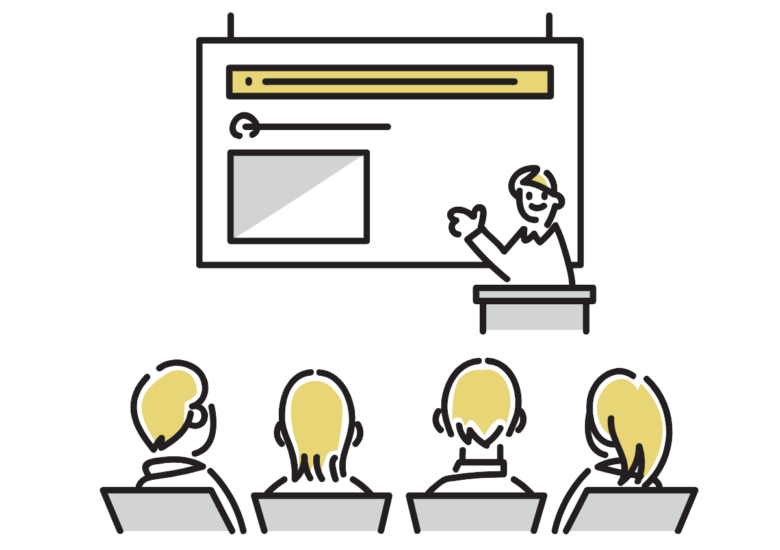
保育の安全対策にお困りではありませんか?
不適切保育や虐待防止策の理解を深めたい

置き去り事故の防止や安全点検を徹底したい

ヒヤリハットを活用して怪我を減らしてたい
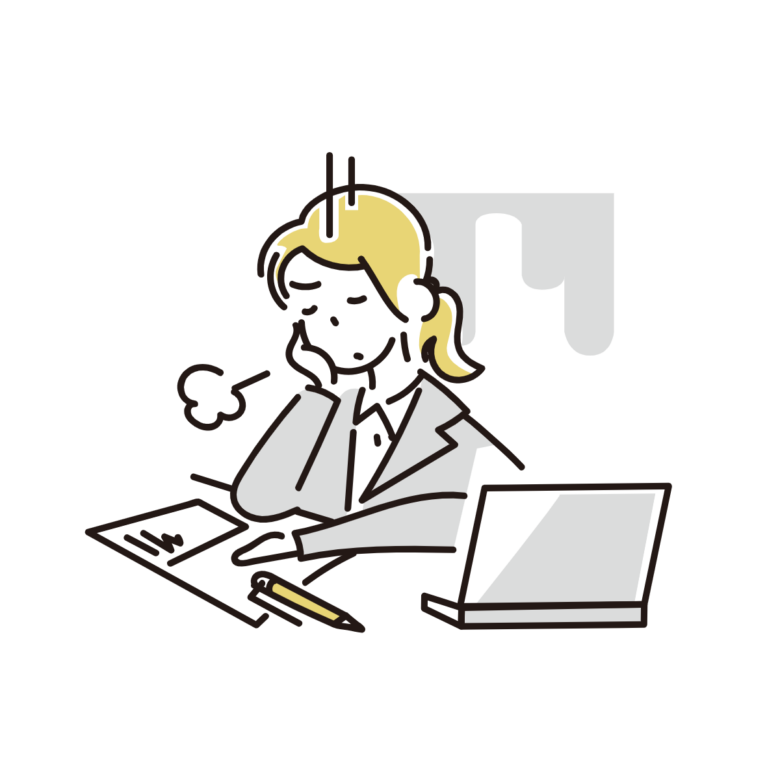

保育の安全管理は子どもの生活の質の向上を目指すものです

救命講習を受けるだけで子どもの命を救えるわけではありません。
昨日できなかったことが、今日できるようになる子どもの目覚ましい成長と、保育者がつくる環境とのバランスが崩れたところに保育の事故は発生します。
事故は重大・深刻なものから、日ごろの小さなケガまで様々です。子どもの生活の質(QOL)の向上を目指して保育の安全対策に取り組む必要があります。
多くの事故は防止可能であり、これによる心停止を未然に防ぐことは重要である。事故は偶発的で避けられないもの(accident)ではなく、防止可能な傷害(injury)ととらえ、不慮の事故による傷害の防止(injury prevention)についての市民啓発が重要である。
出典「JRC 蘇生ガイドライン 2015 オンライン版」第3章:小児の蘇生(一般社団法人 日本蘇生協議会)
オンライン勉強会のお誘い
-

-
参考【月2回、週末に開催/無料】まずは週末の夜に無料の勉強会から参加してみませんか
リスクマネジメント勉強会 ヒヤリハットの活用や、事故防止など保育のリスクマネジメントに関するポイントや、教育・保育施設で求められる衛生管理の具体策について参加者の皆さんと考察する勉強会です。 保育事故 ...
続きを見る
もう一歩、安全を高めるならアドバイザー契約をご検討ください

安全点検の質的評価
安全点検は、当事者の安全バイアス(身近な環境ゆえの思い込み)が邪魔をするものです。第三者の視点を入れることで安全性が高まります

保育防災の対策強化
避難訓練など保育施設の防災対策は、一般知識にならうだけでなく、安全配慮義務にもとづく高度な知識と備えについてアドバイスします

看護職の就業安定化
保育園看護師の離職が増加。医ケア児の保育機会も増加する現代に保育園看護師の存在が大きくなる一方の働きやすさの改革を支援します
契約実績

費用および現地開催・Zoom開催などの実施形式
主催団体、自治体の規定のご予算や実施形式のご要望に合わせます。
※相談は無料。対面ほかオンラインでの事前相談が可能。
※お気軽にお問い合わせください。研修事業を受託するための企画段階で講師の打診をいただくケース
これまでお付き合いのある個人・団体等と、そのご紹介を除いて、受託前段階での打ち合わせほか資料作成について、受託できなかった場合でも、スケジュールの拘束および研修内容の検討の手間が発生するため、原則、有料とさせていただきます。
ご相談の段階でご承知おきください。保育施設の保護者会やPTA向けに講演会をご相談いただくケース
全国の保育施設で子どもの事故、小さなケガをきっかけにした苦情、保護者とのトラブルが増加しています。そのような社会的背景をふまえ、園運営を円滑に進めるためのリスクコミュニケーションを目的とした園内研修の一環として、保護者のみなさんを主に対象としたワークを交えた講演会を実施しております。
職員研修と同様の講演費用などを頂戴しますことをご承知おきください。社内研修用に社内講師が使用する資料やマニュアルの執筆を依頼いただくケース
「社内研修用に社内講師が使用する資料やマニュアルの執筆(作成)」をご相談いただく場合、これまでに、どのような研修を経て、どの段階に達したのか、ご相談元の社内講師が、どういったポイントで資料をお使いになるか、といった、必要なところをヒヤリングした上で(複数回の打ち合わせを行なうことがあります)、研修意図に合わせた資料をご提供いたします。
保育安全のかたち すべての記事一覧
保育事故を SHEL分析で検証する。6つのエラー項目と要因について
認可保育園、認可外保育園で重大事故が発生した際の報告義務化とは、ただ事故の状況説明が求められているわけではなく、再発防止に向けた事故検証が行なわれる際の適当な情報を提供することに目的が置かれています。保育に留まらず、社会全体で子どもの事故・虐待による死亡事例を検証する制度(CDR)の整備が進むことからも重要なテーマと考えられます。 保育事故では事故件数や発生場所のほか、原因物質や傷害の種類などを分類して要因を導く定量分析が一般的ですが、重大事故では、その事故の根底にある要因を深く掘り下げる定性分析の手法 ...
保育指針の健康及び安全につながる保育の事故防止ガイドラインと省令の枠組み
平成30年改定の新保育所保育指針では、保育の安全にまつわる「健康及び安全」が第5章(全7章)から第3章(全5章)へ移動するとともに、具体的な備えとして「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」でピックアップされた「睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面」の重大事故に関する項目が追記されました。 保育指針に具体的な事象が記載されたということは、保育活動を通じて事故が発生した場合の対応だけに留まることなく、日ごろの保育そのものにおいて、安全対策が基盤にあると揺り戻る形 ...
保育のリスクマネジメントの理解(事故防止におけるリスクとハザードの基礎知識)
平成27年度の「子ども・子育て支援新制度」のスタートに伴って、保育施設が遵守すべき園活動における安全についての規定(平成26年内閣府令第39号)が定められました。これまで保育の安全性といえば、事故が起きたときの『直接的な加害性や過失性』によって判断されていましたが、今後は定められた安全基準を満たしているか否かで判断されていきます。 とはいえ利用者が保育施設を安心して利用できる、子どもが安心して遊びこむ保育環境をつくる、そのための安全な保育はマニュアルをつくるだけでは実現しません。『リスクマネジメント』を ...
プールあそびに”安全な水深”がないわけ。保育のリスクとハザードの考え方
「子どもの命を守らないといけない」、保育現場からはそんなメッセージが聴こえる反面、「安全管理は保育を乏しいものにする」とのマイナスイメージも。そこには、子どもの命を守ることも、ゆたかな保育をすることも、どちらも大事だけれど、具体的にどのように両立させていけばいいのかが判らないという、ジレンマに陥った苦しさも見えてきます。 解決するための安全管理の考え方に、あそびにおける「学びのリスク」と「子どもだけでは危険回避が不可能なハザード」があることはご存知でしょう。国交省の「都市公園における遊具の安全確保に関す ...
保育のヒヤリハットの集め方とヒヤリハットを生かした保育の事故防止の方法
保育で、いつからか「ヒヤリハット運動」と呼ばれるものが広がり、ヒヤリハットを集めて事故防止に役立てようという盛り上がりを見せたものの、保育現場からは「ヒヤリハットが集まりません」、「集めたヒヤリハットの活用方法がわかりません」という声がなくなることがありません。その原因を解き明かしながら、対策の必要性までを考えていきます。 ヒヤリハットとは、幸い損害が発生せずに済んだニアミスのこと。子どもがケガをしそうになって、保育者が「ヒヤリ」としたり、「ハッと」肝を冷やして気づいた出来事を言い表したりしますが、目的 ...
「スゴいい保育」に掲載された豊かな保育を実現するリスクコントロールについて
保育のいまの声と必要な未来を伝えるサイト「スゴいい保育」の中の、「シンカする保育(「深化」と「進化」を続ける保育の今をさぐる)」の一番最初の記事として、安全と豊かな保育についてまとめた、『保育士は言わない【危ないから遊んじゃダメ!】という一言。安全と豊かな保育を両立する方法論とは。』を掲載していただきました。 【1/3回】保育士は言わない「危ないから遊んじゃダメ!」という一言。安全と豊かな保育を両立する方法論とは。安全ばかりを優先してもよい保育ではない(中略)保育者向けの、現場に必要なリスクマネジメント ...
保育園の午睡にベビーセンサーは必要か?保育園のベビーセンサーの望ましい使い方:後編
保育所等における業務効率化推進事業の実施以降、保育施設向けベビーセンサーが開発されたり、現場に導入されたという話が盛んに聞かれるようになりました。以前、実際のところベビーセンサーとはどういったものか、保育施設でどのように活用していけばいいかについて記事を書きましたが、関連して神奈川県主催で開催された研修会資料の一部を公開します。 平成30年度、第2回私設保育施設等 保育担当者 事故防止研修会「睡眠時の事故防止と保育施設でのベビーセンサーの使い方」(講師・文責:株式会社保育安全のかたち 遠藤登) ベビーセ ...
保育園の午睡にベビーセンサーは必要か?保育園のベビーセンサーの望ましい使い方:前編
「保育園にベビーセンサーは必要か?」 保育園の導入事例が増えるに比例して、導入を迷う声も聞かれます。それは保育現場に選択肢に対する情報が満足に共有されていないことが一因ですが、2018年末時点の答えはというと「なくても構わない」ものです。ベビーセンサーに限らず「IoT関連商品」は保育者の業務軽減が役割とされています。 保育者の睡眠の見守り業務は子どもの命を守ることです。しかし現時点のベビーセンサーは子どもの命を守ることはできません。 2019年2月に神奈川県で開催される認可外保育所職員向けの研修(保育園 ...
ベビーセンサー:睡眠の見守り行為を補足する製品を導入する場合の考慮ポイント
保育園のお昼寝時間に、「うつぶせ寝による窒息が疑われる」死亡事故の発生が度重なっていることから、お昼寝時間の保育者の見守り方法に大きな注目が集まっています。うつぶせ寝の防止などルール化されているものの、昨今、保育現場の人手不足が深刻なこともあって、俗に「ベビーセンサー」と呼ばれる保育者の見守り行為を補足する製品の導入が進んでいます。 このベビーセンサー(以下、お昼寝時間の見守り行為を補足する製品)類の機能説明にある、「眠っている乳児のカラダの動き、呼吸の停止や継続的なうつ伏せ寝状態を検知した場合に警告を ...
保育園のお昼寝の呼吸確認は人工呼吸じゃなくて補助呼吸の考え方が正しい
東京と大阪の保育施設で、うつぶせ寝を原因とした窒息で、同じく1歳の子どもが亡くなりました。睡眠中の安全について、保育の安全研究・教育センターの掛札先生がお書きになったので、突然死リスクの低減と異常の早期発見に対して参考になさってください。 睡眠中の安全(2016年4月14日)1)窒息死の予防最低限0、1歳クラスでは、まず窒息死を予防する行動をします。窒息死は予防できる死亡であり、予防の取り組みをしなかった場合は過失を問われる可能性もあります。引用:保育の安全研究・教育センター http://daycar ...
乳幼児突然死症候群と夜泣き
SIDS:乳幼児突然死症候群を防ぐためだと言っても、長年、保育現場で保育者が子どもに対してうつぶせ寝で寝かせる行為がなくなりません。乳幼児突然死症候群を防ぐためにやってはいけないとされる、うつぶせ寝のほか、暖めすぎたりタバコの煙に曝される環境がなぜダメなのか、実は保育者がよく分かっていないという声と関係があるのかもしれません。 乳幼児突然死症候群(Sudden Infant Death Syndrome)とは、「元気に育っていた赤ちゃんが、事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡する病気」だと厚労省が定 ...
寝返ってうつぶせ寝だったときの呼吸確認方法を蘇生ガイドラインから考える
2011年に入って、消防署をはじめとした普及団体の心肺蘇生法のやり方が、2010年日本版蘇生ガイドラインを土台にしたものへ更新されました。現時点の変更点は、「心肺停止かを判断する呼吸確認のやり方の変更」と、「人工呼吸と胸骨圧迫の順番の入れ替え」、そして「胸を押すテンポのアップ」と「押す深さの修正」といっていいと思います。 ここでは、この新たな呼吸の確認方法を例に、午睡中の子どもに対する呼吸確認の方法について、特に『気が付いたら子どもが寝返っていた』場合に、とにもかくにも早急に呼吸ができているかを、うつぶせ ...
保育園給食の高温スープを1歳児にこぼさせた火傷事故の要因の予測と再発防止策
愛知県知多市にある保育園で1歳児が大やけどを負うといった事故が発生しました。会見によると「子どもの手の届く範囲にカートを入れたのは落ち度があった。救急車を呼ぶべきだったが、職員の車で搬送してしまった」そうです。また保育士が目を離した隙に、給食を運んだワゴンの上の鍋に1歳児が手を伸ばしたことでスープがこぼれたことから、知多市幼児保育課からは給食用のワゴンを子どもに近づけない、スープの温度を下げるといった指導が行なわれています。 子どもが高温火傷を負うといったような事故は、ほかの種類の重大事故に比べてきっか ...
さいたま市保育園のプール死亡事故報告書を読み解いて安全なプール開きを実施しよう
猛暑が予想される今夏。梅雨明けとともに水あそびやプール開きを考えている保育施設も多いことでしょう。同時に水あそびの規模やプールの大きさに照らして一律に安全対策を求められても困ると感じている現場の声もお聞きします。しかしプール開きにあたっては「私たちは大丈夫だから」ではなくて、客観的に大丈夫と検証できるように備えることが大切です。 2017年8月に発生したプール死亡事故の「監視の目を離さない、水面から目を離さないことを徹底していたが穴があった」(園長談)という穴とは何だったのか、すべての保育施設で子どもた ...
さいたま市保育園のプール死亡事故の報道から見えた危機管理の問題点
2,016年7月に発生した認定こども園のプール事故につづいて、2,017年8月にさいたま市にある保育所プールで重大事故が発生しました。前者の事故が、33人の園児が50センチ以上の水かさのプールに入水し、保育者が2名だけであったことが事故を防げなかった原因のひとつとして検証報告が行なわれたものの、教訓は生かされることがないまま死亡に至りました。 監視担当であった保育者2名ともが、子どもたちが入水している最中にプールに備え付けてあった滑り台の片付け作業を行なったそうで、子どもたちから目が離れたことが今回の重 ...
保育施設のお正月行事で子どもとお餅を食べる際に最低限抑えておくべき安全確認ポイント
2016年の元日も高齢者を中心とした窒息事故が複数件起きました。高齢者にとってお餅は危険ですが同様に幼児期の子どもにとっても最も危険な食べ物のひとつです。保育施設で安易に食べさせているとは言いませんが、「食文化の継承」を理由にお餅を食べさせるのは止めるのも大切な選択肢といえるほどです。お餅が子どもにとって危ない理由は「事故が起きているから」というだけのものではありません。お餅という食べ物と、子どもの体の仕組みにかかわる問題です。 子どもがお餅をおいしく食べるには、まず安全であってこそです。お餅を小さく切る ...
プールあそびの危機管理を大和市幼稚園教諭のプール水死事故から考える
大和市の学校法人西山学園「大和幼稚園」のプール遊びの水死事故で、業務上過失致死罪に問われた元担任教諭に対して、求刑通り「罰金50万円の判決」が出ました。この事故が起きたひとつひとつの事象を自らの保育に照らしてみて、もし同じ事柄が見受けられたら、同様に子どもの命を失うような重大な溺水事故を起こす可能性があるのかもしれません。 ここまで2年半の長い月日が流れています。「園児の安全配慮に対する認識や自覚が乏しく、幼稚園教諭としての基本的注意義務に違反」しないようにするために、『プール内で園児らの安全を守るため ...
お泊り保育で重大事故を防止しながら思い出をつくるためのリスクマネジメント
保育園児がひとり、お泊り保育の夜に入った温泉施設で溺れて意識不明の重体となる事故が起こりました。園児が溺れた湯船の中に大人は居らず、引率した保育所職員は溺れたところが見えていなかったと言います。 起訴内容によると引率した保育所職員は園児を湯船に残して、湯船が死角となった場所で自らの髪を洗っていたそうです。保育の重大な事故のひとつとして再発防止策を導くためのリスクマネジメントを考えていきます。 宿泊保育で男児重体 入浴中に意識不明 西予市宇和町明間の明間保育園(西谷邦子園長)が7月中旬に行った宿泊保育で、近 ...