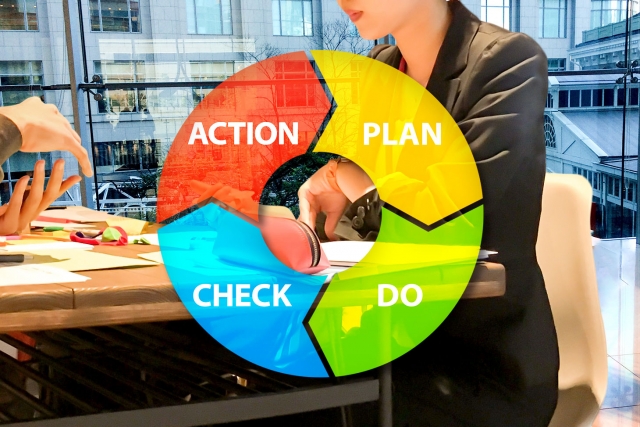| 講座テーマ | 第一回講座 保育のヒヤリハットの理解を深めその活用方法を考える |
| 開催日時 | 5月31日(金)20時から(120分)募集終了 |
| 7月12日(金)20時から(120分)募集終了 | |
| 8月10日(土)20時から(120分)質疑応答延長あり | |
| 講座テーマ | 第二回講座 保育事故の分析手法「保育cSHEL」の基礎を学ぶ |
| 開催日時 | 6月7日(金)20時から(120分)募集終了 |
| 7月13日(土)20時から(120分)募集終了 | |
| 8月17日(土)20時から(120分)質疑応答延長あり | |
| 講座テーマ | 第三回講座 ヒヤリハットなど事故事例を検証するワークショップ |
| 開催日時 | 6月21日(金)20時から(120分)募集終了 |
| 7月26日(金)20時から(120分)募集終了 | |
| 8月31日(土)20時から(120分)質疑応答延長あり | |
| 参加費 | 1回あたり:4,000円(税込) 3回一括お支払い:9,800円(税込) |
保育における子どものケガの原因を検証する方法を参加者のみなさんと振り返りながら、ヒヤリハットを活用して保育の質を高めつつ事故を防止していくための連続講座です。
保育現場の事故報告書には子どものケガの様子と、ケガをした子どもの近くにいた保育者の反省文が記載されています。望ましい事故報告書からは客観性のある検証結果と具体的な再発防止策について読み取れる必要があります。保育施設における事故報告書の書き方や検証方法について段階的に一緒に学びましょう。
危機管理担当者向け保育の事故検証方法を学ぶ講座概要
事故検証(保育cSHEL)方法を学ぶ 3回講座受講対象者
- 保育に従事して安全管理を担う看護職の方
- 子どものケガが頻発する理由を知りたい保育者
- 保育事故に関心のある方
- 保育行政に携わる方
- 保育の安全に興味関心をもってる方
第一回講座 保育のヒヤリハットの理解を深めその活用方法を考える
第一弾は事故防止の基本とされる「ヒヤリハット運動」について学びます。ヒヤリハットが集まらない、ヒヤリハットを集めても取り扱い方が分からないと悩んでいませんか。ヒヤリハットにこだわれば保育が管理主義になって好ましくないとの勘違いも生まれています。事故防止はもちろん、ヒヤリハットの反省を促して意識を高めさせるのではなく、保育の質を高めるための仕組みづくりについて皆さんと考えます。
講義で用いるツール:安全管理マトリックス。ヒヤリハット活用の仕組みづくり

ヒヤリハットをただ集めればいいわけではなく、そのことを通して、何が見えていて何が見えていないのか?見えていない部分の事故を防ぐためにどうすればいいのか?ここまでの対策ができて初めて事故予防と言えるのだとわかりました。
全体を俯瞰しながら子どもたちを見守るという動きも、自分では心がけていますが、全職員が同じように見守るためには、もっと具体的な動き方を共有するという点が不足しているとわかりました。ヒヤリハットの検証方法も合わせて、よく理解できていない部分をもっと深め、施設の安全対策に役立てられればと思います。
第二回講座 保育事故の分析手法「保育cSHEL」の基礎を学ぶ
ヒヤリハットとケガをともなう事故との違いが解ったところで、第二弾では保育における事故の検証方法「保育cSHEL」について学びます。保育現場で発生した重大事故を地方自治体に届け出る報告書の書式には、事故原因を検証するための「SHEL分析モデル」が組み入れられています。保育事故の検証に適した SHEL の書き方についての理解を深めながら、ヒヤリハットもふくむ保育事故の検証方法について考えます。
講義で用いるツール:保育cSHEL。保育の課題検証のための仕組みづくり

自分が危険だと思う事と、他の人が危険だと思う事が異なるので、どれだけお互いの危険予測を伝え合い共有できるかが大切で、また、その伝え合うための仕組みを作っていかなければならないと感じました。
私の中で特に印象的だったのは、見えてない事象が一番危険という事でした。見えてない可能性を極力減らすためにも、事前の危険予知を徹底していきたいと考えます。
この度はご指導いただきまして、誠にありがとうございました。
ちなみに、保育救命の本も日々活用させていただいてます!
第三回講座 ヒヤリハットなど事故事例を検証するワークショップ
勤務園でヒヤリハットを活用する、保育事故を検証して課題解決につなげるためには、まずは実際に参加者個人が SHELを使いこなすことが必要です。第三弾は、ヒヤリハットや重大事故の事例をもとに参加者同士がSHEL分析を通じたディスカッションを重ねながら、実践につなげるための方策について考えます。

受講したあと指導計画の様式に、取り組み内容から予測される危険とその対策を記入するようにしました(実際に使用するのは次年度から)。その上で、ヒヤリハットは想定外の危険に気づけた(ギリギリではあったが事故を未然に防げた)ポジティブなできごとと認識して、積極的に報告・共有する、という意識づけを行うようにします。
これまでも「遊びの充実と安全の確保は両立できる」という信念で保育に携わってきましたが、その両方の視点を明確に取り込んだ様式を導入したり、ミーティングや園内研修の形式を見直すところから始めます。
参加日時を選んで参加チケットをご購入ください
※ 連続講座のため可能な限りひとつ目からの受講をおすすめします。
| 講座テーマ | 第一回講座 保育のヒヤリハットの理解を深めその活用方法を考える |
| 開催日時 | 5月31日(金)20時から(120分)募集終了 |
| 7月12日(金)20時から(120分)募集終了 | |
| 8月10日(土)20時から(120分)質疑応答延長あり | |
| 講座テーマ | 第二回講座 保育事故の分析手法「保育cSHEL」の基礎を学ぶ |
| 開催日時 | 6月7日(金)20時から(120分)募集終了 |
| 7月13日(土)20時から(120分)募集終了 | |
| 8月17日(土)20時から(120分)質疑応答延長あり | |
| 講座テーマ | 第三回講座 ヒヤリハットなど事故事例を検証するワークショップ |
| 開催日時 | 6月21日(金)20時から(120分)募集終了 |
| 7月26日(金)20時から(120分)募集終了 | |
| 8月31日(土)20時から(120分)質疑応答延長あり | |
| 参加費 | 1回あたり:4,000円(税込) 3回一括お支払い:9,800円(税込) |
| 重要 | 特定商取引法に基づく表記 |